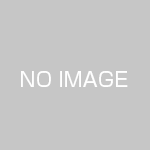こんにちは。
カラダ支援アシスト整体院です。
熱中症対策として、まずは体の仕組みについてお伝えしています。
自律神経の不調を抱えている人の中には頻尿の方もいます。
また高齢の方で頻尿に悩まされている方も少なくありません。
実は頻尿も熱中症と関係があるので、今回は「排尿と体温調節」についてお伝えしたいと思いす。
排尿は体内の余分な水分や老廃物を排出することで、血液の濃度や血圧を調整します。
これにより、体液のバランスが保たれ、結果的に体温の安定にも関与しているので、暑い時には排尿によっても体温調節が行われているのですが、排尿は汗よりも水分の放出量が多いため、頻尿があると水分が外に出すぎてしまうことがあります。
これは競技中のアスリートが倒れてしまうような脱水の状態まではいかなくとも、頻尿や日頃からあまり水分を補給しないことで軽度の脱水状態が起きている人は珍しくありません。
脱水状態になると体はそれ以上の脱水を防ごうとして、汗をかかないようになります。一般的には汗をかくことで排尿回数が減る傾向がありますが、頻尿は自律神経のエラーからくる要素が大きいので、一般的な理屈に合わないことが起こリます。(ちなみに寒い時に頻尿になるのは「寒冷誘発性排尿反射」といって、寒さという刺激そのものが膀胱の反射的な収縮を起こして排尿を促しています。)
前回の記事でもお伝えしたように、汗をかかない状態は体内の放熱が妨げられ、体温が上昇起こりやすくなります。頻尿によって汗が出づらくなってしまうと熱中症のリスクは上がってしまうのです。
ストレスと体温調節
体温調節は主に脳の中の視床下部というところで行われていますが、熱の産生には甲状腺や腎臓、心臓も大きく関わっています。
ストレスが多くなると脳の視床下部の機能が低下を起こします。視床下部は全身のホルモンの指令系統で甲状腺や副腎とも関連が深いので、甲状腺や副腎の機能低下に繋がってしまいます。特に甲状腺は熱産生に関係しているので体温調節が難しくなるのです。
こうしたストレスによる身体反応は発生しやすい部位がそれぞれ個体差があるので、脳にエラーが出やすい人もいれば皮膚に出やすい人もいるし、心臓や腎臓に出やすい人もいます。何れにしても日頃からのストレスケアはとても重要になってきます。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。