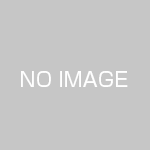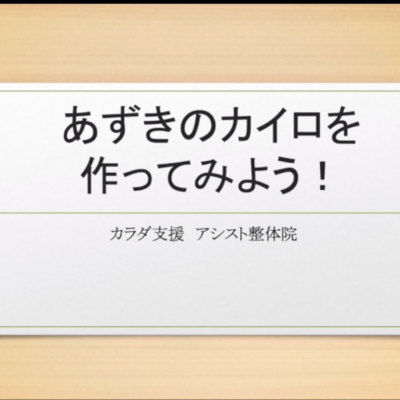こんにちは。
カラダ支援アシスト整体院です。
今回は甘い物と糖尿病についてです。
糖尿病とは膵臓で分泌されるインスリンというホルモンの分泌が少ない、またはタイミングが遅い、インスリンの働きが弱いなど、何らかの理由でうまく血糖の処理ができなくなると、血糖値が下がらなくなり、食後数時間たっても、血糖値が下がらない状態が慢性的に続いてしまう病気です。
1型糖尿病
インスリンをつくっているすい臓のβ細胞が壊れてしまうタイプ。
自分の体内でインスリンをつくりだすことができなかったり、ごくわずかしかつくれないので、体の外からのインスリン補給(インスリン注射)が絶対的に必要となります。
2型糖尿病
いわゆる生活習慣病として有名な糖尿病の約95%がこのタイプと言われています。
すい臓がつくるインスリンの量が少ない、またはインスリンが出ても働きが悪い場合、その両方が混ざって発症するタイプです。
要因として肥満、飲酒、喫煙、運動不足、遺伝、高血圧、ストレスなどから以前は、中高年の人に発症することがほとんどでしたが、食生活をはじめとするライフスタイルの欧米化により、今では若い人や子どもにも増えています
自覚症状がないうえ、高血圧や心筋梗塞、脳卒中などを合併するリスクが高い。
妊娠時糖尿病
妊娠すると、胎盤からでるホルモンの働きでインスリンの働きが低下します。また胎盤でインスリンを壊す働きの酵素がでるとも言われています。そのため、妊娠するとインスリンが効きにくい状態になり、血糖が上がりやすくなります。
中でも一番身近なのは2型糖尿病です。
生活習慣は日々のストレスが大きく関与してきます。
たとえば糖尿病と因果関係の深い「甘い物」は脳にとって「報酬」になります。
「報酬」は自分の欲しいものを手にするための原動力になります。
本来は
・感謝された
・人の役に立てた
・これだけのことをやり遂げた
・尊敬する先輩から認めてもらえた
といったように、仕事や人との関わりの中で満たされることが多いものなのです。
もちろん給料という形でも表現されるので、頑張った分が給料に反映されていればそれも文字通り「報酬」になります。
しかし、現代人の多く自分自身の感覚が低下してしまい、自分が何をしたいのか?なんのために働いているのか?がわからないまま生きているので、仕事や人との関わりのなかで、そうした報酬を受け取ることが少なくなってきています。
そうなると手っ取り早い報酬が「甘い物」になりやすいのです。
また、こうした生き方はエネルギーの回復が低下していきますので、疲れやすく結果的に運動したいという意欲も低下するので、ますます生活習慣病が加速していく身体環境になっていくのです。
報酬は脳内でドーパミンという神経伝達物質が関与しているのですが、ドーパミンが増えすぎると満たされる感覚が低下していき、甘い物だけでなく、ゲームやスマホ、ギャンブル、恋愛、ドラッグなど様々な「依存症」に繋がります。
脳内セロトニンによってドーパミンの暴走を抑制することがわかっています。
依存症にまでなってしまうと、多方面からの取り組みが必要になってきますが、そうなる前にしっかりとセロトニンを活性化させることが大事です!
最後までお読み下さりありがとうございました!